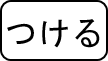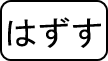第一日野幼稚園の様子(上⇒下:最新⇒旧です)
![]() オークランドからお客様が来ました(2)
オークランドからお客様が来ました(2)




式典の後には、各学級で行っている遊び(お正月遊びや伝承遊び)を一緒に楽しみました。お客様は、お手玉、かるた、すごろく、コマ、ふくわらいなどの遊びを、子どもたちと楽しんでくださいました。子どもたちは、かるたの遊び方やコマの回し方などを知っている英語を使ったり身振り手振りで伝えようとしたりなど、一生懸命コミュニケーションをとろうとしていました。また、ニュージーランドの玩具をプレゼントしてもらい、使い方も教えていただきました。子どもたちは興味津々で話を聞いていました。
最後に、「Tank you very much」「See you again!」と、通訳の方に教えてもらった英語で挨拶をしてお別れしました。子どもたちは、外国の文化に触れるとともに、日本のことも伝えることができてとても喜んでいました。心を込めてプレゼントも準備するなど、お客様をお迎えする『おもてなしの心』も育むことにつながりました。
![]() オークランドからお客様が来ました(1)
オークランドからお客様が来ました(1)




品川区教育委員会が行っているオークランド教員招致の事業で、幼稚園にニュージーランドのオークランド市から、2名の教員が来園しました。オープニングセレモニーとして、年長さくら組が、運動会で踊った『爽涼鼓舞』を披露しました。その後は、ちゅうりっぷ組・さくら組みんなで、お客様を歓迎する式を行いました。
式の中では、ニュージーランドのことや日本に来ての感動など、様々なことを教えていただきました。また、普段楽しんでいる手遊びをお客様と一緒に、英語バージョンで歌ったり楽しんだりしました。日本の歌も聞いていただき、子どもたちはたくさんの拍手をもらいました。
![]() 学校給食
学校給食



毎週金曜日は、5歳児さくら組の小学校給食の日です。
4月当初に比べ、子どもたちの食べる量が増えたことを感じています。お皿がピカピカになったり、おかわりをしたりする子どもが増え、食缶が空っぽになることもあります。
今日のメニューは、「ビスキュイパン・ボルシチ・ゆで野菜にんじんドレッシング・牛乳」でした。
今日もたくさん食べました。ごちそうさまでした。
![]() 大きな大根が収穫できたよ
大きな大根が収穫できたよ





5歳児さくら組が、土づくりから行い、種を撒き、袋の中で大切に育ててきた大根が、収穫の時期を迎えました。力いっぱい何度も引っ張らないと抜けないくらい、大きな大根に生長しました。お店で売っているような大根を収穫できたことに、子どもたちは、驚きながら大喜びしていました。抜いた後の袋の中を見ると、深くまで穴があり、「ここに大根があったんだね」と、面白さと不思議さも感じている様子でした。
土から半分顔を出している大根を見ながら、「大根って、土の上に伸びるのかな?土の中に伸びるのかな?」と問いかけると、「途中までは上に伸びて、途中からは下に伸びるんじゃない?」などと、個々に考えていることを言葉に出していました。新たな知識を知りたいという子どもたちの興味につながるとよいですね。
![]() 預かり保育で調理室からの「おやつ」の提供が始まりました
預かり保育で調理室からの「おやつ」の提供が始まりました



土日、祝日、年末年始以外の日の、教育時間の前後(7時30分~9時/14時(水曜は12時)~18時30分)で、実施している、幼稚園の預かり保育「こあら組」のおやつが変わりました。
これまでは、市販のおやつで対応されていましたが、今後は保育園と同様のおやつが調理室より提供されます。
子どもたちも、今日の献立は何かな?と楽しみな様子です。毎日、おいしくいただいています!
![]() 音楽会ごっこ
音楽会ごっこ





さくら組の保育室では、数名の子どもたちが集まり、音楽会ごっこをしていました。少し先にある音楽会で演奏する曲や歌う歌、ダンスなどを、自らする遊びの中で再現しながら遊んでいます。
友達と相談しながら、デッキで音楽を掛け、一人が何個も楽器を担当したり交代したりしながら、繰り返し演奏を楽しんでいます。途中からは、「音楽会」のプログラムどおりにミニ音楽会を開催することにした様子です。入場から始まり、プログラムどおりに自分たちで音楽会ごっこを進めながら遊ぶことを楽しんでいました。
学級のみんなで合わせて合奏をしているのは、一日に数回のみです。学級での取組が楽しいものであったり、「もっとやりたい」と子どもたちが自然に思えるような活動であるからこそ、自ら選んでする遊びの中でも、取り組もうとする姿が見られるのだと思います。
傍では、他の遊びをしている子どもたちがいます。その子どもたちも、チラチラと音楽会ごっこの様子を気にしたり、歌を一緒に口ずさんだりしていました。「音楽会」という学級全体での目的を一人一人が意識し、それぞれの関わり方で取り組もうとしている様子がよく分かりました。
![]() 音楽会に向けて
音楽会に向けて



音楽会に向けて、ちゅうりっぷ組では、ダンス、楽器遊びなどを学級の皆で楽しんでいます。
テンポのよい音楽に合わせて、体を伸び伸びと動かして踊ったり、楽器の扱い方を担任の先生と確認しながら親しみのある曲に合わせて演奏したり、大きなお口を開けて歌を歌ったりと、4歳児らしく表現遊びを楽しんでいます。
楽器遊びでは、先生の合図をよく見たり音楽をよく聞いたりしながら演奏しています。また、担任が弾くピアノの音をよく聞きながら大きな声を出して歌も歌っています。お友達と音が揃う楽しさや声が揃う心地よさを繰り返し感じているちゅうりっぷ組の子どもたちです。
![]() やっしーの表現遊び
やっしーの表現遊び




講師の方をお迎えし、4歳児・5歳児が一緒に表現遊びを楽しみました。
普段から、歌ったり踊ったりすることが大好きな子どもたちです。ドングリになりきってコロコロと転がって遊んだり、ビニル袋を使って踊ったり、くだものに見立てたカラーボールのお買い物をし、買った果物をバルーンに広げてミックスジュースを作ったりなど、なりきったり、見立てたり、踊ったりと、様々な表現遊びを楽しみました。最後には講師の方のギターによる歌を聞きながら子どもたちが動き出すと、自然と全員での一つの輪ができあがりました。その様子に心が温かくなりました。
今後の保育の中でも様々な場面で、自分なりに表現する幼児の姿が見られることでしょう。一人一人が感じたことや考えたことを様々な方法を使って表現する姿を大切にしていきたいと思います。
![]() 秋がいっぱい
秋がいっぱい






ちゅうりっぷ組では♪「どんぐりころころ」の歌を楽しんで歌っています。
保育室に行くと、折り紙でどんぐりを製作していました。折り紙で折り、顔を描いて手と足を付けると、自分のどんぐりの完成です。どんぐりを保育室の壁面に飾ると、どんぐりころころの歌が聞こえてきそうな壁面になりました。その他にも、ちゅうりっぷ組の保育室には、秋がいっぱいあふれています。自分たちの体験を基にしたものが身近な環境としてあることで、自然に自分たちの生活と結びつき、体験を振り返ったり、子どもたちの興味や関心がより深まったりすることにつながっていきますね。
![]() 様々な表現遊び-楽器を使って-
様々な表現遊び-楽器を使って-



4歳児ちゅうりっぷ組の楽器遊びの様子です。カスタネット、鈴、タンバリン、トライアングルと、学級の皆で一つずつ扱い方や鳴らし方を知らせながら、音の違いなどを楽しんできました。リズムに合わせて演奏することやお友達と音が揃う楽しさなども感じています。
自ら選んでする遊びの中でも、楽器を持ち込んだり、空き箱などを使って自分で製作した楽器を使ったりしながら、コンサートごっこを楽しむ様子も見られています。
![]() 芋掘り体験を生かして-さくら組-
芋掘り体験を生かして-さくら組-




年長児さくら組は、新聞紙を丸めて白い紙を貼り、その上に絵の具で色を付けたお芋を作っていました。自分たちが掘ってきたお芋をよく見ながら、大きさや形にこだわって作る様子が見られました。色付けでは、自分で絵の具を混ぜたり、場所によって塗る色を変化させたりなど、一人一人が細かいところまで、よく見て、よく考えながら、工夫して作る様子が見られました。
経験を再現する方法は様々あります。それぞれの子どもたちの発達に合わせ、子どもたち自身が楽しみながらできる方法で芋掘り遠足の体験を再現していることが印象的ですね。
![]() 芋掘り体験を生かして-ちゅうりっぷ組-
芋掘り体験を生かして-ちゅうりっぷ組-



芋ほり遠足の後、4歳児ちゅうりっぷ組は、みんなで大きな紙に絵の具を使ってお芋の色に塗ることを楽しんでいました。みんなで色を塗った大きな紙を担任がお芋の形にし、壁面に飾りました。自分たちの経験したことが身近な環境としてあることが、子どもたちの安心した生活環境につながったり、自分たちの体験を思い出したりすることにつながったりしています。
![]() 芋掘り遠足2-竹藪探検隊-
芋掘り遠足2-竹藪探検隊-



弁当後には、芋畑の隣にある竹藪の散策を行いました。急な坂道を下り竹藪の中を抜けていくと、今度は上り坂が・・・はじめは恐る恐る試していた子どもたちですが、慣れてくると坂をスイスイと下りたり駆け上ったりと、周回コースを繰り返し走り回って楽しんでいました。自然の中で心も解放された様子で、思い切り体を動かしながら「楽しい~!」という声があちらこちらから鳴りやまない時間になりました。
![]() 芋掘り遠足1
芋掘り遠足1




とてもよい天気の中、バスに乗って芋ほり遠足に行ってきました。土を一生懸命掘り進めると、中から様々な大きさや形のお芋が出てきました。子どもたちは、土の中からなかなか出てこないお芋に苦戦したり、掘れたお芋の形に驚いたりしながら楽しみました。
芋掘り後はみんなでお弁当を食べました。お空の下で食べるお弁当はさらにおいしく感じました。
園内でも様々な栽培活動をしていますが、いつもとは少し異なる場所、広いお芋畑での、貴重な収穫体験となりました。
![]() ラーメン屋さん
ラーメン屋さん



レストランの近くに、ラーメン屋ができました。こちらも本物のような美味しそうなラーメンがお客さんの前に並んでいます。友達と一緒に考えたり工夫したりする様子が見られるようになってきたさくら組の子どもたち。ラーメン屋の名前を友達と一緒に一生懸命考えて決めたそうです。お店には、子どもたちが作成した看板やメニューもあります。「文字を使うと相手に伝えることができるんだ!」「字を書いて表現してみたい」「字を使うって楽しいな」など、子どもたちの必要感に応じて、文字への興味・関心や書いてみたいという意欲を丁寧に育んでいきたいと思います。ラーメン屋ごっこでも、「看板を作りたい」「メニューを作りたい」などという子どもたちの気持ちから、そのような姿が育まれていることがよく分かりました。
![]() レストランごっこ
レストランごっこ





年長児さくら組の保育室では、素敵なレストランができあがっていました。子どもたちが、大型積み木などの様々な遊具を扱いながら組み合わせてレストランの場を作り出しています。テーブルの上には、本物のような料理が並んでいました。子どもたちは、コックさんやウェイトレスになりきってお客さんに声を掛けながら、料理を作ったり提供したりしています。遊びに必要なものを細かいところまでこだわって作ったり、作ったものを使って遊んだりすることを楽しんでいます。レストランには自分たちで作ったメニューもあり、メニューの説明を一生懸命している子どももいました。遊びには何が必要なのかを考え、友達と一緒に楽しみながら遊びを進めている様子がよく分かりました。4歳児ちゅうりっぷ組のお客さんも訪れ、「美味しそう」などと言いながら楽しんでいました。
![]() 違う国の話を聞こう/いろんなサッカーを知ろう(多様性や多文化理解を大切に)
違う国の話を聞こう/いろんなサッカーを知ろう(多様性や多文化理解を大切に)





サッカー体験とともに、コーチが住んでいたことのある国の話や、様々な種類のサッカーの話を聞く時間がありました。4歳児ちゅうりっぷ組は、違う国の話に興味津々です。「羊がたくさんいるんだよ」「こんな食べ物があるんだよ」と海外の異なる文化に触れ、驚く様子も見られました。
年長児さくら組は、いろいろな写真を見ながら、性別関係なくサッカーをしていること、車いすでするサッカーがあることなど、様々な方が行うサッカーがあることの話を聞きました。ブラインドサッカーというサッカーは、音のなるボールを使うことを知り、驚く子どもたち。コーチと一緒に実際にボールに触れたり蹴ったりしてみました。「難しいよー」「音をよく聞くとわかるかも」などと、思ったことをありのままに伝えながら体験していました。このような体験を通して、少しずつ多様性の理解や多文化理解につながっていくことを感じました。
![]() サッカー体験
サッカー体験




2回目のサッカー体験を行いました。4歳児ちゅうりっぷ組は、コーチに親しみの気持ちを感じ、楽しみながらボールを一生懸命追いかける姿が見られました。さくら組は、年長児らしくボールを扱ったり、コーチの足元からボールを取ろうとしたりしながら、思い切り体を動かすことを楽しんでいました。子どもの視点に立って関わってくれる大好きなコーチと一緒に走り回り、サッカー体験をすることを、どの子どもも笑顔いっぱいで楽しんでいました。
![]() 10月10日は目の愛護デー
10月10日は目の愛護デー



看護師による健康教育で、『目』についての話を聞きました。数字にちなんで10月10日は目の日であること、髪の毛が目にかかっていると目が悪くなってしまうことなど、たくさんの話を聞きました。
日々の生活の中で目を大事にすることの大切さを知り、自分の生活を振り返るきっかけになったことでしょう。最後には、「視力検査」の話も聞きました。これまでの自分の経験を基に、看護師とやり取りをしながら様々なことを学んでいました。
![]() ♪トンボのメガネは何色メガネ?
♪トンボのメガネは何色メガネ?



4歳児ちゅうりっぷ組の保育室では、トンボの製作を楽しんでいる子どもたちがいました。トンボの目の部分にカラーセロハンを貼り付けて様々な色の目のトンボを作っています。いくつか色を組み合わせてみたり、同じ色で二つの目を作ったり…一人一人の子どもが自分のトンボに思いを込めて作っている様子が見られました。童謡『とんぼのめがね』を学級で歌うことも楽しんでいる子どもたちです。何色メガネのトンボになったかな?
![]() たのしかったね!運動会
たのしかったね!運動会




運動会終了後の子どもたちの様子です。運動会で行った競技や演技を再現しながら遊ぶ子どもたちの姿が見られています。4歳児ちゅうりっぷ組では、担任が準備していたちゅうりっぷ組用の法被を着て、年長児が行った踊りを再現しながら遊ぶ様子が見られています。その様子に5歳児さくら組の子どもたちも踊り方を教えながら一緒に踊り始める姿もありました。また、リレーごっこを楽しむちゅうりっぷ組の子どもたちに、さくら組がルールを一生懸命伝えながら一緒に楽しむ姿も見られました。ちゅうりっぷ組の、さくら組への憧れの気持ちが大きく育っている様子がよく分かります。
「運動会が楽しかった!」という思いをもっているからこそ、「自分たちでやり遂げた」という達成感や満足感を感じたからこそ、見られる姿だと感じています。行事を教育活動の一環として捉え、運動会までの過程や運動会当日から得られた経験を大切にしながら、今後の教育活動につなげていきます。
![]() 小学生との関わりを運動会に取り入れて
小学生との関わりを運動会に取り入れて



運動会の前日、5歳児と5年生との交流が行われました。「5年生が見てくれる!」と、意欲たっぷりの子どもたちでした。たくさんの拍手とよかったところの感想をもらい、運動会当日に向けてより意識が高まった様子でした。
また、5歳児が行う係活動の一つには、応援団があります。今日は、小学校運動会のときの6年生の応援団長が、昼休みの時間を使い、幼児たちに応援の仕方を教えに来てくれました。応援団長2人の声の大きさや動きを見ながら、驚きながらもニコニコの笑顔で、真似をして挑戦する子どもたち。「もっと膝を曲げて!」「もっとお腹から声出して!」と、かっこよく応援するための方法をたくさん教えてもらいました。
小学生への憧れの気持ちが深まったり、親しみの気持ちを感じたりすることにつながる活動になりました。
このような活動が実現できることも、身近に小学生の姿があり、園の子どもたちと小学生・幼稚園教諭と小学校教諭とが自然と関わりをもち、連携を図ることで可能となる、第一日野幼稚園ならではの恵まれた環境であるからこそだと実感しました。
![]() 広い場所で伸び伸びと
広い場所で伸び伸びと



運動会に向けて、本番と同じ小学校の体育館で表現の練習をしました。
4歳児ちゅうりっぷ組は、自分なりになりきって「がおー!」と、元気いっぱい掛け声を掛けながら表現を楽しんでいます。
5歳児さくら組は、腕を伸ばしたり顔の向きを揃えたりなど、本格的に細かな部分にも意識をもちながら取り組んでいました。そして、踊りが終わると、自分たちが着ていた衣装の法被を丁寧にたたむ姿が見られました。使用する衣装が大切なものであることを自覚し、時間が掛かっても一人一人が、最後まで行おうとしている姿に感動しました。
衣装を大事に扱う姿からも、運動会で自分たちが行うことをしっかりと理解し、やり遂げようという気持ちをもち、意欲的に活動に取り組んでいる様子が見られました。幼児教育で育てることが大切であるといわれている「心情・意欲・態度」が育ってきていることがよく分かりました。
![]() 気持ちを揃えてみんなで踊ろう
気持ちを揃えてみんなで踊ろう

さくら組の保育室に行くと、担任が映っている映像が流れていました。その近くには、興味をもった子どもたちが集まり、映像を見ながら踊りを楽しんでいます。さくら組が、10月に行われる運動会の演技を踊り始めた様子です。遊びの中で踊りを取り入れながら、少しずつ学級のみんなにも広がり、みんなで声を揃えたり、動きを揃えるための方法を考えたりしながら取り組んでいます。小学校のアリーナでも踊り、手を伸ばすことや動きを止めることなどを意識しているようです。年長児らしい姿がたくさん見られています。
![]() 冬野菜を育てよう
冬野菜を育てよう



年長児さくら組が冬野菜の栽培を始めました。今回は、大根やブロッコリーの栽培に挑戦するそうです。土づくりをし、丁寧に大根の種を撒いたり、ブロッコリーの苗を植えたりしていました。これまでの経験から、土づくりや種まき、水やりなどはすっかり慣れた様子です。経験の積み重ねの大切さを感じました。たくさん収穫できるとよいですね。
![]() 玉入れ遊び
玉入れ遊び




ちゅうりっぷ組が玉入れ遊びをしていました。これまでは、担任が段ボールで作った口を開けた動物の口を目掛けてボールを投げる遊びを楽しんでいました。
今日はカゴが登場し、カゴの中に玉を投げ入れて遊びました。担任の「よーい、ピー!!」という笛の合図に合わせて玉を投げます。何度も玉を拾って投げる幼児、手の中にたくさん玉を持ってからまとめて投げようとする幼児など、自分なりに一生懸命考えながら楽しむ姿が見られました。玉を投げ入れた後には、担任と子どもたちが一緒に「いーち、にー、さん、し、ご・・・」と玉の数を数えます。たくさん入ったことに飛び跳ねながら喜ぶ子どもたちの様子が見られました。
笛の合図を聞いて動いたり、数を数えたり・・・玉入れ遊びを通して、ルールを守って遊ぶと楽しくなることを感じたり、数への興味も育まれたりしています。
少しずつ日々の保育の中に運動会につながる活動を取り入れるようになってきました。日々の中で楽しんでいる子どもたちの遊びや生活を行事に自然につなげていけるよう、担任の先生たちは、様々なことを考え、保育を組み立てています。
![]() 8月生まれの誕生会
8月生まれの誕生会





8月生まれの子どもたちの誕生会を行いました。ちゅうりっぷ組には先生から、さくら組には友達が作った贈り物がプレゼントされました。司会をするさくら組の子どもたちも少しずつ、自信をもって話をする様子が見られるようになってきました。今日のお楽しみは、先生方による影絵クイズです。様々に変装した先生方に子どもたちは大興奮。どの先生が出てくるのかを楽しんでいました。
影絵には、子どもたちが遊びで使用しているOHPを使いました。誕生会を通して感じたOHPを使って遊ぶ面白さが、今後の子どもたちの遊びにもより生かされていくことでしょう。
![]() 鬼遊び
鬼遊び



ちゅうりっぷ組が戸外で鬼遊びをしていました。友達に関心をもったり関わることが嬉しくなってきた子どもたちです。先生や友達の様子をよく見ながら、逃げたり友達にタッチしようとしたりしています。みんなで「きゃー」と言いながら逃げ回ることを楽しみ、ちゅうりっぷ組のみんなで一緒にする活動を楽しんでいる様子が見られました。
![]() 夏の話を共有しよう
夏の話を共有しよう




さくら組では、夏休みの話を学級の皆に伝える時間を作っています。行った場所や楽しかったことなどを自分の言葉で友達に伝えます。みんなの前で話すことや友達に聞いてもらうことを喜びながら、毎日、友達の話に興味をもち、耳を傾けている様子が見られます。「どうやって話したら友達に伝わるかな?」ということに気が付けるよう、担任が傍で知らせています。
話をしている子どもたちの横には、日本地図・世界地図、車・飛行機など乗り物のイラストがあり、行ったところを地図の中から探して、その場所にシールを貼ったり、何で行ったのかなどをイラストで示したりもしています。
『日本には、自分が住んでいるところ以外にもいろいろな場所があるんだな』『遠いところへ行くときは、飛行機に乗っていくんだね』『日本以外の国もあるんだ』などと様々なことを感じています。このような体験が、様々な場所や地図、乗り物などへの興味へつながっていきますね。
![]() 切手を貼って、届けよう!
切手を貼って、届けよう!





近隣の郵便局から、局員さんをはじめとした局員の方が来園し、子どもたちに郵便についての話やポストの話をしてくれました。絵本や写真などを見せてもらい、子どもたちは興味津々で話を聞いていました。「パンダの方のポストがあるよ」「ポストって赤だけじゃないんだね」など、自分が思ったことを口々に伝えていました。質問タイムでは「ポストの中ってどうなってるの?」などという質問もとびだし、局員の方に丁寧に答えていただきました。子どもたちはいろいろなことを知る喜びを感じている様子でした。
また、郵便を届けるためには住所を書くこと・切手を貼ることも教えてもらいました。先日作成したファミリープレゼントに、みんなで切手を貼り、大切なプレゼントを届けてもらえるよう、「よろしくお願いします。」と、郵便屋さんに渡しました。
![]() 製作遊び(ファミリープレゼント)
製作遊び(ファミリープレゼント)




ちゅうりっぷ組は、ハサミや糊などの用具やカラーセロハンなどの材料使い、製作遊びをしていました。さくら組は、画用紙を細かく切ったり貼ったりビーズを使ったりしながら製作をしています。
9月は敬老の日があり、敬老の日にあわせて、ご家族の方に向けてのプレゼントを作っている様子です。
ちゅうりっぷ組は、自分の顔が付いたキラキラのしおりが、さくら組は自分で顔を構成した土台に付箋をつけた付けたメモができあがりました。
プレゼントを届けたい人のことを思い浮かべながら真剣に製作を進める様子が見られました。
![]() みんなが揃って嬉しいね
みんなが揃って嬉しいね






2学期の初めの頃の様子です。ちゅうりっぷ組の部屋に入ると、友達の名前を呼ぶ声がたくさん聞こえてきました。久しぶりに会う友達との関わりを喜んでいる様子です。さくら組も学級の皆で揃って2学期を迎えた喜びを感じながら遊びだす姿が見られています。早速、小学校の体育館に行き、みんなでトラックリレーをして遊んでいました。走り方やバトンの渡し方など、ルールを理解しながら体を動かし、活動を楽しむ様子が見られました。
![]() 始業式-2学期が始まりました!-
始業式-2学期が始まりました!-



始業式を行い、本日より2学期が始まりました。
始業式では、2学期の園生活や予定されている行事の話などを聞き、子どもたちは、園生活に期待をもっている様子でした。その後、さくら組では、夏の間の話を先生や友達に話したり、友達に何があったのかを聞いたりする姿がたくさん見られていました。
![]() 盆踊りの練習‐地域とのつながりを大切に‐
盆踊りの練習‐地域とのつながりを大切に‐


地域で開催される夏まつりが近付いた頃、預かり保育こあら組が、盆踊りの練習に参加しました。
小学校の体育館に、日ごろからお世話になっている町会長さんや、地域の町会の方、小学生、小学校の先生などが集まり、地域の方に教えていただきながら、みんなで盆踊りを踊りました。初めての踊りもありましたが、こあら組の子どもたちは真似をしながら一生懸命踊っていました。昨年まで、園で一緒に過ごしていた小学生のお姉さんやお兄さんや兄弟関係で顔見知りの小学生などから、親しみをもってたくさん声を掛けてもらい、嬉しそうな様子が見られました。地域の方々との触れ合いも大切にしていきたいですね。
![]() 学校給食
学校給食



4月から始まった週に一度の学校給食。繰り返し体験することで慣れてきた様子が見られます。お箸を使って食べたり牛乳パックの扱い方を覚えて自分で扱ったりしながら、おいしい給食をいただいてきました。
最近では、準備や片付けは、子どもたちが自分でトレーを持って進めています。トレーの持ち方、食器の扱い方など、丁寧に扱うことの大切さを繰り返し伝えていきたいと思います。
毎回、小学校の栄養士の先生が、配膳の補助や献立の説明に来てくださり、子どもたちの食べる様子を把握してくれたり、子どもたちとの会話を楽しんだりしてくれました。幼稚園にいる時期から子どもたちの実態を把握していただけることのありがたさを実感しています。2学期もよろしくお願いします。
![]() スイカの重さはどのくらい?
スイカの重さはどのくらい?




園で育てていたスイカも収穫しました。収穫したスイカを見た子どもたちは、「重いの?」「どのくらい重い?」とスイカの重さを知りたい様子でした。実際に測ってみよう!と、体重計に乗せてみると『0.95kg』。身体測定で測った自分の体重の数字と比べている子どももいました。『実際に手に持って』また『体重計に乗せて数字を見て』など、様々な方法で重さに関する興味を深めている様子が見られました。
子どもたちの前でスイカを切ってみると、中は、種がたくさん入った赤いスイカでした。子どもたちは「わー!!」と声を上げながら、育てたスイカを見ていました。
![]() トウモロコシの収穫
トウモロコシの収穫







5歳児さくら組が、水や肥料をあげて大切に育ててきたトウモロコシの収穫を行いました。一つの茎に大きさの異なる実がいくつかついていました。収穫した後は、みんなで皮をむいてみました。おひげだらけのトウモロコシをよく見ながら「毛がたくさんついてるね」「力を入れて引っ張れば皮がむけるよ」と、お友達と力を合わせて皮むきをしていました。トウモロコシの皮をむいてみると、上から下までたくさん黄色い実をつけているもの・芯は大きいのに黄色い実は少ししかついていないものなど、様々なトウモロコシがありました。
さらに、芯にたくさんついている黄色い実は小さいのに、少ししかついていない実は大きい?!など、子どもたちは、収穫したトウモロコシから様々なことを発見して口々に話し、自然の不思議さや面白さをたくさん感じている様子でした。その後、甘いトウモロコシをみんなでいただきました。
他にも、夏季休業中前にたくさんのものを収穫できました。自分たちで育てたものをお友達と一緒に食べ、食物への興味の深まりや食べる喜びを感じられる食育体験につながりました。
![]() 様々な遊具や用具を遊びに取り入れて
様々な遊具や用具を遊びに取り入れて




5歳児さくら組が、影絵やブラックライトを使って遊んでいました。
遊びの初めは、担任が影絵クイズを行い、どのような機器を使って影を映しているのか伝えたり、影の不思議さや面白さを学級の皆で共有したりしました。その後、扱い方を伝えながら遊びの中に提示すると、子どもたちは、様々なものを映して形の面白さを楽しんだり、自分たちで描いた絵に色を塗って映したり動かしたりすることを繰り返し試しながら楽しんだりしていました。
また、七夕のときにみんなで見て楽しんだ、ブラックライトを使って遊ぶ姿も見られました。
ライトを当てると光る紙を担任が準備しました。それを使い、星や花火などを製作し、ライトを当てると光ります。子どもたちは、光ることの不思議さに驚きながら遊びを楽しんでいました。また、先日見たプラネタリウムを再現してお話を作り、楽しむ様子も見られました。
![]() 4歳児と4年生の交流
4歳児と4年生の交流


今年度2度目の4歳児と4年生の交流を行いました。
4年生が4歳児のことを考えて準備してくれた遊びや、4歳児が普段楽しんでいる遊具を使って一緒に遊びました。4年生は「どこで遊びたい?」「こういう風にするんだよ」などと、とっても親切に言葉を掛けてくれました。4歳児は、4年生に親しみの気持ちをもち、安心して遊びを楽しむ様子が見られました。4年生が手を取って教える姿や背中にそっと手を伸ばす姿に、思いやりの気持ちをたくさん感じました。
![]() 夏まつり
夏まつり




園の夏まつりが行われました。朝、5歳児が園の周りをお神輿を担いで周りました。職員が準備したお店周りの後は、小学校のアリーナ(体育館)に集まり、みんなで盆踊りを楽しみました。いつも子どもたちを温かく見守ってくださる地域の町会長さんも来園し、一緒に踊ってくださいました。季節を感じられるよい行事となりました。4歳児ちゅうりっぷ組は、5歳児からお神輿を借りて園庭を担ぎました。重さに驚きながら、自分たちの飾りがついたお神輿を担げる嬉しさをたくさん感じながら楽しんでいました。
![]() お神輿をつくろう
お神輿をつくろう



夏まつりにむけて、5歳児さくら組がお神輿を作りました。みんなで相談をして、何色のお神輿にするのかを決めたり形を考えたりしました。段ボールに紙を貼った後、色を塗ってお神輿の形が出来上がると、子どもたちは大喜びでした。お神輿には、5歳児はアイスクリームを製作して飾りました。4歳児が製作した花火も飾られています。自分たちで製作したお神輿があることで、夏まつりへの期待が膨らんだ様子です。
![]() 作ったものを使って
作ったものを使って




4歳児ちゅうりっぷ組の子どもたちは、様々な材料を使って作ることを楽しんでいます。最近では、作ったものを自分たちの遊びの場所に持ち込んで、使いながら遊ぶ様子も見られるようになってきました。ごちそうに見立てたり、パソコンでゲームをしたり、バーベキューでお肉を焼いて食べたり、綿あめを作って先生やお友達に食べてもらったり……イメージ豊かに4歳児ならではのごっこ遊びを楽しんでいます。
![]() チョウチョになったよ
チョウチョになったよ





各保育室で育てていた蛹がチョウチョになりました。チョウチョは広いところに飛ばしてあげたいな。と、チョウチョとお別れをして、逃がしてあげることにしました。子どもたちは「元気でね~」と笑顔で見送っていました。
5歳児さくら組では、担任が、蛹から蝶になる瞬間の動画撮影に成功しました!
子どもたちはキラキラとした表情で、蛹からチョウが出てくる動画を夢中で見つめていました。「こんな風にチョウチョになるんだ!!」と不思議さや面白さを感じ、興味や関心を深めていました。
![]() 水や泥の感触を味わって
水や泥の感触を味わって

4歳児ちゅうりっぷ組が砂場で遊んでいます。裸足になり、水の心地よさや泥の感触を味わうことを楽しんでいます。何度も繰り返し水を運び、川を作ったり池を作ったりして遊んでいます。
![]() 音楽鑑賞会「みんなのことば」
音楽鑑賞会「みんなのことば」


「みんなのことば」が来園し、音楽鑑賞会を行いました。
フルート、バイオリン、ビオラ、チェロの楽器の演奏を聴きました。本物の楽器の音色や楽器が何でできているのかなどの話を聞き、子どもたちは驚いたり喜んだりしていました。会の中では、幼稚園の歌や親しみのある曲を演奏していただき、自然と体でリズムにのったり、手拍子をしたりしている様子が見られました。
この体験を日々の保育の中でも生かしていきたいと思います。
![]() 健康教育
健康教育

さくら組は、月に一度、保育園のナースによる健康教育を実施しています。今回は「からだ」についてのお話でした。
「自分の体は全て大切なところ。。。」これから水遊びも始まります。今日聞いた話を思い出しながら生活を進めていけるとよいですね。
![]() パトロール中です。敬礼!
パトロール中です。敬礼!


なりきって遊ぶことが大好きな4歳児ちゅうりっぷ組の子どもたちは、積み木でパトカーを作り、警察官の帽子や制服を着て遊んでいます。「悪い人はいないかな」とパトロールをしたり、捕まえた人(担任)に事情聴取をしたりと、自分なりになりきって表現しながら遊ぶことを楽しんでいます。
今日は、パトロール中に本物の警察官に出会った様子です。敬礼をしてしっかりと挨拶をしていました。
![]() 交通安全指導
交通安全指導


大崎警察の方が来園し、交通安全指導を行いました。安全についての紙芝居を見たり、洋服の色によって夜道での運転手からの見え方が異なることを知ったりなど、交通安全について子どもたちは、興味津々で話を聞いていました。実際に信号機を見ながら横断歩道を渡る体験も行いました。「何のために手を挙げるのかな?」という問いかけにも一生懸命考えていました。しっかりと手を挙げて、上手に横断歩道を渡ることができました。
![]() 外国の文化を知ろう
外国の文化を知ろう


サッカー体験の後、5歳児さくら組は、講師の先生のこれまでの経験を基に、ニュージーランドの食べ物や文化などについて教えてもらいました。
「ニュージーランドってどこにあるんだろう?」と話しながら地球儀を見たり、ニュージーランドで有名なスポーツについて教えてもらったりしました。国旗に興味をもっている幼児もいました。
このような体験を積み重ねることが、多様性の理解や多文化共生につながっていきますね。
![]() サッカー体験
サッカー体験






品川区教育委員会が実施している「しながわ多様性理解・多文化共生推進事業」の一環として、講師を招聘し、各クラスでサッカーの体験をしました。
ボールを持ち、コーチの真似をしながら体を動かしたり、合図に合わせて動いたりすることを楽しんでいました。最後は、コーチvs子どもたちで試合を行いました。広い第2グラウンドで一生懸命ボールを追いかけ回って遊び、どの子も伸び伸びと体を動かしていました。コーチにも親しみの気持ちをもって触れ合う姿がたくさん見られました。
![]() 芝生気持ちいいな!
芝生気持ちいいな!


5歳児さくら組が、芝生でみんなで体を動かして遊んでいました。
気持ちのよい天気の中、芝生で思い切り体を動かして遊ぶ心地よさを味わっています。
友達の動きや声を聞きながらルールを理解して遊びを楽しむ姿が見られました。
![]() 試したり工夫したり考えたり…
試したり工夫したり考えたり…






年長児さくら組の子どもたちは、すり鉢やすりこ木を使い自然物から出る色での色水遊び、また、大型積み木、サインペン、段ボールなどを使ったごっこ遊びなどを楽しんでいます。様々な用具や遊具、素材を使いながら、考えたり、試したりしながら繰り返し取り組んでいます。やりたい遊びをする中で、自分なりに工夫してじっくり遊んだり、友達と関わり合いながら一緒に遊んだりする楽しさを感じています。
![]() 積み木楽しいな
積み木楽しいな


ちゅうりっぷ組の部屋では、中型積み木で遊ぶ子どもの姿が見られました。
中型積み木は、様々な形を組み合わせるとベッドや車、バスなど、いろいろなものに変化します。子どもたちは、どのようにして使えば安全に楽しく遊ぶことができるのかを担任の先生と一緒に確認しながら扱って遊ぶことを楽しんでいます。
積み木でできた救急車やパトカーにのり、救急隊や警察官が、患者さんを運んだりパトロールをしたりと大忙しの様子です。
![]() 降園前の活動(5歳児)
降園前の活動(5歳児)


5歳児さくら組の降園前の様子です。
先生のピアノに合わせてみんなで声を揃えて歌をうたったり、絵本を見たりして、降園前の時間を過ごしています。一日の楽しかったことや嬉しかったことを順番に話をする日もあります。さくら組の一日のまとめと次の日への期待をもてるように配慮して生活の流れを作っています。
年長になってから頑張っている当番活動は、自分たちで次の友達へ引継ぎを行っています。自分たちで生活を作っていこうとしている様子がよくわかりますね。
![]() 5歳児学級活動
5歳児学級活動



5歳児さくら組の学級活動の様子です。
年長になって一カ月が過ぎ、4歳児のときに楽しんでいた遊びや、新たなルールの遊びを学級のみんなで楽しんでいます。少しずつ友達への意識も深まり、同じチームの友達を応援したり、上手くいく方法を教えたりする姿も見られるようになってきています。小学校のアリーナで、思い切り体を動かして鬼遊びをするなど、担任との関わりを楽しむ中で、信頼関係が深まる様子も見られています。
![]() 離任式
離任式



他園へ異動された先生とのお別れの会を行いました。
子どもたちは、当日の朝から、久しぶりに大好きな先生に会えることに期待をもつとともに、少し緊張している様子も見られました。式の前には、「もうすぐだね」「一緒に給食も食べたかったね」などと話しながら、会場の準備に取り組んでいました。異動した先生から、新しい幼稚園の話を聞いて驚いたり、みんなが心を込めて作ったプレゼントや歌を送ったりし、素敵なひとときが過ごせました。
![]() 4月の誕生会
4月の誕生会








4月生まれのお友達の誕生会を行いました。
年長児は、前の日に誕生会に向けて司会の練習をしたり、みんなで力を合わせて装飾を作ったりして準備を進めていました。「お・た・ん・じ・ょ・う・び・お・め・で・と・う」の順番に貼ろう!と、様々に順番を変えながら貼ってみるなど、文字に興味や関心をもって関わる様子も見られていました。
年少児にとっては初めての誕生会です。歌を歌ったり、パネルシアターを見たりする中で、みんなで一緒に集まってお祝いする楽しさを感じました。
年長児は最後の片付けまで頑張りました。友達や年少児の役に立つ嬉しさを感じながら、自分たちで誕生会を作り上げようと取り組んでいました。
![]() 4歳児学級活動
4歳児学級活動



4歳児ちゅうりっぷ組の子どもたちの学級活動の様子です。幼稚園での生活にも慣れ、学級のみんなで一緒に活動することも楽しんでいます。担任の先生と一緒にみんなでダンスを踊ったり、歌を歌ったり、パネルシアターを見たりしています。
降園前には、担任の先生が読む絵本のお話を聞いたり絵を見たりすることを喜ぶ様子も見られます。降園準備など、身の回りのことも少しずつ自分の力で進めようとする幼児が増えてきました。小さなことですが子どもたちにとって大きな成長の一つですね。
![]() のりを使ったよ(4歳児こいのぼり作り)
のりを使ったよ(4歳児こいのぼり作り)


4歳児ちゅうりっぷ組は、のりを使ってこいのぼりを作りました。
ぐるぐる指を使ってのりを伸ばすよ、貼った後はぺたぺた指で押さえてね、などと糊の使い方を一つ一つ丁寧に確認しながら進めました。
自分のこいのぼりができあがると、大喜びの子どもたち。
こいのぼりを持って戸外へお散歩に行ったりチョウチョと一緒に飛ばして遊んだりする様子が見られました。
![]() 染め紙でこいのぼり作り(5歳児)
染め紙でこいのぼり作り(5歳児)



5歳児さくら組が染め紙をして遊んでいました。紙を広げたときの模様の面白さや不思議さに驚く様子が見られ、繰り返し楽しんでいました。
その後、染め紙を使ってこいのぼりの製作をしました。
友達と2人で、それぞれの作った染紙の鱗を貼り付け、相談しながら目玉も付けました。「友達と一緒に力をあわせたらできた!」という体験が、友達関係の深まりにつながっていきます。
![]() 4月 避難訓練
4月 避難訓練



今年度初めての避難訓練を行いました。4歳児ちゅうりっぷ組は、年長さくら組が避難訓練を行う様子を見学しました。放送や先生の話をよく聞いて、話をしないでスムーズに避難をしているさくら組の様子を、真剣な表情で見ていました。ちゅうりっぷ組はお部屋に戻ってから、防災頭巾のお話を聞いて、実際に被る練習をしていました。
![]() 週一回の学校給食が始まりました!
週一回の学校給食が始まりました!




年長児さくら組が今年度初めての学校給食体験を行いました。
小学校の栄養士さんから、給食のメニューや使っている食材を教えてもらったり、牛乳パックの開け方を教えてもらったりしました。子どもたちは、「スパゲッティ大好き!」「ケーキもあるよ」と嬉しそうな表情で食べていました。学校給食体験を通して、小学校就学に向けての安心感や期待感につなげていきたいと思います。
今年度は、5月から、週に1回学校給食をいただく予定です。
![]() ちゅうりっぷぐみの様子no.2
ちゅうりっぷぐみの様子no.2



戸外では、砂場を好んで遊ぶ幼児が多くいます。また、テラスに置かれた製作材料を使ってチョウチョを作り、広い芝生を飛ばしたり、お花の蜜が大好きなチョウチョに蜜を上げようとしたりしていました。
芝生校庭では、伸び伸びと体を動かして走ったり寝転んで心地よさを味わったりする幼児もいます。広い芝生や様々な植物がある園ならではの経験ですね。
![]() ちゅうりっぷ組の様子
ちゅうりっぷ組の様子

入園してから少しずつ幼稚園の生活に慣れてきたちゅうりっぷ組の子どもたちです。
保育室の中にある様々な遊具に関わってみようとしたり、自分のしたい遊びをしたりなど、自分の安心できる居場所を見付けて過ごしています。4歳児の初めの頃は、安心して生活する中で、まずは、自分のやりたい遊びを自分なりに十分に楽しんで遊ぶことが大切です。
![]() 安全指導
安全指導





ちゅうりっぷ組が安全に楽しく園庭で遊べるように、さくら組が遊び方を教えてくれました。
「こっちだよ!」「ゆっくりでいいからね」と優しく声を掛けながら、遊び方を教えたり、見守ったりする
さくら組の子どもたち。年長児として自分たちの力を発揮したことがまた1つ自信となりました。さくら組に遊び方を教えてもらった後、ちゅうりっぷ組だけで園庭で遊びました。自分から遊具に関わってみたり、思い切り体を動かしたりして楽しみました。
![]() はじめましての会
はじめましての会



4歳児ちゅうりっぷ組と5歳児さくら組が「はじめましての会」を行いました。
会が始まる前には、さくら組がちゅうりっぷ組のためにいすを並べたり、司会の練習をしたりと、張り切って会の準備に取り組みました。幼稚園の歌を歌ったり、それぞれの学級で楽しんでいるダンス「ぐっぱ!」を一緒に踊ったりしました。これから、4・5歳児が関わる中での子どもたちの育ちも大切にしていきたいと思います。
ーーー令和7年度 第一日野幼稚園の様子ーーー
更新日:2026年01月16日 17:12:20